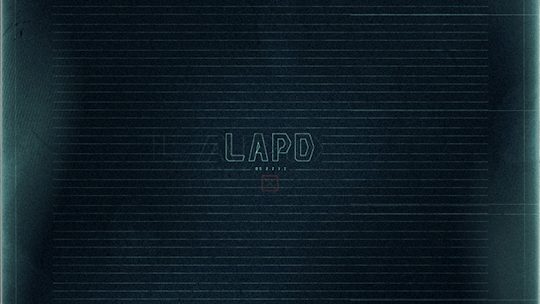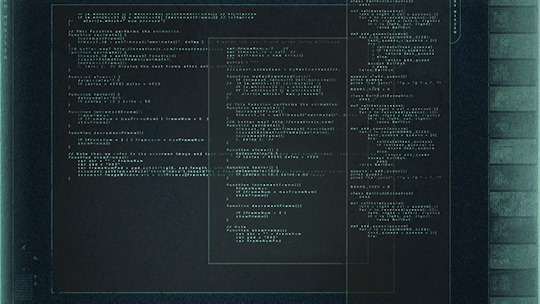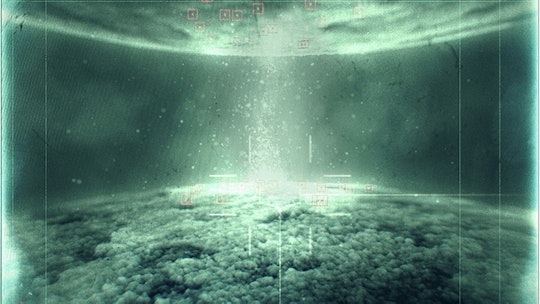Blade Runner 2049 アルコン・エンターテイメントのブレードランナー2049と共に未来に, Territory Studio と Cinema 4D
過去40年間の中において、今見ても色褪せない映画を一つあげるとすればそれはブレードランナーだろう。フィリップ・K・ディックの短編小説を元にしたこのサイバーパンク映画は、画期的なビジュアルとこれまでにない退廃的な近未来を表現した作品としてさまざまな分野に影響を与えている。そのため、アルコン・エンターテインメントによる1982年のリドリー・スコットの傑作の続編は、計り知れない期待とそれに関わるすべてのVFX会社へ大きなプレッシャーがのしかかった。
まずは、ブレードランナー2049のスーパーバイジング・アートディレクターのポール・イングリスがプリプロダクションのために、Territory Studioへアプローチしたから始まったという。Territoryのクリエイティブリードであるピーター・エセゼンニが、初期コンセプトについて語ってくれた。「最初は具体的な説明はありませんでした。私たちはブダペストに行き、ポール・イングリスとデニス・ヴィルヌーヴ監督から、映画のテーマとブレードランナーの世界観(オリジナルから30年後)における進化と文脈の概要を聞きました。また、我々は物語に適合するデバイスには、どんなテクノロジーがフィットするのか、テクノロジーは大きなテーマのコンテキストにおいてどのように見えるべきであると感じているかについて話し合ったのです」
タスクは、LAPDオフィスのモニター、ウォレスラボラトリーとデッカードのペントハウスの内部のさまざまなスクリーンのグラフィックを作成することだった。チームのコアメンバーの6人から、必要に応じて最大10人まで増やし、2016年の5月から11月まで作業を行い、15のセット向けに100を超えるオリジナルスクリーンが制作された。
しかし、元の映画から単純に発展させるではなく、デニス監督は、デジタルの機能とファイルが抹消される大きな出来事が発生した世界と仮定した。それは、技術が発展するであろう土台となるもので、何か存在すればそれは大きな困難となる。「物語のためデザインとプロットやキャラクター、演技をサポートする物語のためのデバイスのビジュアル制作において、高度に実験的なアプローチを自信を持って行えたのは、私たちにとって深い体験でした。デニス監督は、直接元の映画をリファレンスすることは望んでいませんでしたが、そのテクノロジーをはっきり知覚できることを求めていました。我々の仕事は、既存の技術を再発明することでした。彼のテクノロジーに対する指示は、有機的、抽象的、光学的、そして物理的なものであるというkとでした。そのため、このプロジェクトでは、デザインされたインテーフェイスを投影するのではなく、すべてのシステムは映像の制作、光学効果、投影といったテクノロジーにようるものでした」(ピーター談)
“Cinema 4Dの使いやすさとスピード、安定性のおかげで厳しいスケジュールを守りながら、実験を行うことができたという。”
それがはっきりとわかるのは、検死のシーンだ。前作でデッカードが使っていたテクノロジーを少しリファレンスにしているが、よりメカニカルで光学的なフレームワークを組み込まれた。Territoryが担当したのは、電子顕微鏡で骨組織を拡大していく一連の画像の作成で、それをより物理的でドラマチックにした。アート部門が参照した骨盤を使い、骨組織が拡大され抽象的になっていく一連の画像を作成した。それは、光学レンズが物理的に切り替わることで拡大されるメカニズムで、オフィサーKとジョーシ、そして観客がシリアル番号に気づくシーンだ。「これは、極めて重要で、しかも複雑なショットでした。シーン全体で慎重に演出が行うため、セットにリアルタイムに画像が表示され、俳優はそれを見ながら演技が行えるようにしました」
実際は、Cinema 4Dで作業を始める前に、たくさんのプランがあった。Territoryのチームは、LEDスクリーンの生物発光の代替方法の研究と実験する時間を費やした。彼らは、光学レンズ/プロジェクターとマクロ写真によるフォトジオメトリ(果物/肉)であるグラフィック技術と組み合わせた実験も行った。実験プロセスは、のちに別のユニークなエフェクトの開発に繋がった。それは、LAPDのベースラインでレプリカントであるオフィサーのメンタルの状態のスキャンテストのシーンで使われた。前作のように虹彩を表示するのではなく、新しいテストでは視神経を通る視野を表示し、レプリカントの神経活動を表現した。その意図は、人間の脳やニューロンを映し出すのではなく、美的感覚が有機的な性質を持つようなイメージを抽象的に達成することだった。これは、乾燥したグレープフルーツのおかげだ。
しかし、Cinema 4Dを使ったより伝統的なCGテクニックを使った他のシーンもあった。Territoryは、NAP(隣人のアパート)のシーンでシミュレーションを使用した。オフィサーKが見つけた小さな木馬をスキャンしてカットだ。ピーターはそれがどのように行われたかについて詳しく説明してくれた。「私たちはおもちゃをモデリングして、その内部をX-Particlesで行った流体シミュレーションを行いました。私たちは、パーティクルの動きをセットに合わせてディレクションするため、タービュランスを中心にいろいろなモディファイアを使いました。我々はまた、『パイロット・フィッシュ』と呼ばれるドローンと一部スピナーのシーンでも、外部環境が通常と異なる雰囲気見えるようにパーティクルシミュレーションを使用しました。これらのシミュレーションの有機的、混沌とした性質は、雰囲気の向上に貢献しました。
アンドリュー・A・コソブ、ブロデリック・ジョンソン、シンシア・サイクス・ヨークイン、バド・ヨーク・ヨークンが制作した映画の多くは、暗闇にネオンが光る高いコントラストのシーンを生み出した。この上に大気の塵や汚れが加えられた。CGによるディスプレイをスクリーン上に他のものと一致させることは、いくつかの問題をもたらしました。ピーターは、これに対してどのようにアプローチしたか解説してくれた「私たちは、コンセプトアートにアクセスすることができたので、ショットの意図についてかなり良いアイデアが得られましたが、ロジャー・ディキンズからTerritoryに提供したアニメーションを使用していくつかカメラテストを行い、特定のセットでのライトレベルを確認しました。ロジャーが製作したライティング設定に合わせて、LAPDのシーンのカラーを調整しました。さらに、デニス監督から出演者の顔にスクリーンからの反射光を要求されたのでそのテストも内部で行いました」
オフィサーKのスピナーのナビゲーションや通信、スキャン、監視モニターのセットでもケースもあった。スクリーングラフィックスは、レプリカントとブレードランナーとしてKの低い地位を反映させ彼のスピナーとモニターは古くボロボロである必要があった。スクリーンの焼き付き、ゴーストやグリッチ、色の劣化、テクスチャエフェクトは、すべてCinema 4Dで作成され、時代遅れの技術で作られたことを表現した。
Territoryの仕事は、最終的に数テラバイトのデータと1時間以上の動画コンテンツに上り、それらはプロダクションや他のVFX会社に渡され、それぞれのショットに組み込まれた。
こうした難しく注目を浴びるプロジェクトにおいて、ピーターは次のことを認めてた。「Cinema 4Dの使いやすさとスピード、安定性のおかげで厳しいスケジュールを守りながら、実験を行うことができました」
Duncan EvansはDigital Mayhem:3D Landscapes and Digital Mayhemの著者です。
3D Machineと3D Artist magazineの立ち上げた編集者
Territory Studio Website:
www.territorystudio.com